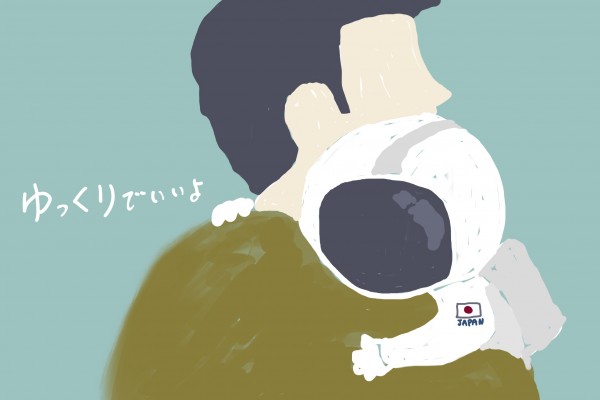【インド旅篇 その3】
事件当日。前日の洪水との激闘で疲れていたのか。その日は出歩かず、部屋で静かに原稿を書いていたい気分だった。宿は、ガンジス川に面していて、窓からエイヤと飛び込めるほどだ。
今回の旅では、観光客が泊まるような3つ星のホテルではなく、人々の日常の隣に身を置きたいと思い、なるべくその地域の普通の暮らしに近い環境を選んだ。食事の準備の音、祈る音、「早く起きなさい」と子どもを叱る母の声、鼻歌などの生活音も、ご飯のにおいも感じる距離感。旅行としてその場所を通り過ぎただけでは、わからないことばかり。暮らすというか、滞在して体験したい。そういうつもりだった。ぼくの一人部屋の状況はこうだ。
・クーラーはない
・お湯はでない
・ガラス窓は閉め切っていなければならない(猿が入ってくるため)
・ 湿度は高く、常に濡れている(衛生状態はよくない)
・洗濯物は部屋干し(猿にとられるため)
・小さなたくさんの虫(蚊、ハエ、羽アリ、いろいろ)
・ヤモリ、へびが部屋に入り放題(大きな隙間があるため)
・停電がある(1日に4,5回。短い時は15分ほど、長い時は3,4時間)
・電球がひとつしかなく薄暗い(4つ中3つの電球が切れている)
不便なこと、暑いこと、虫や動物たちとの共存にはすぐ慣れたのだけど、清潔でないというところはなかなか受け入れられなかった。外を歩くとゴミに溢れていて、必ず牛糞を踏む。その靴で部屋に上がるので、部屋の床は汚れ、匂いが充満する。換気もうまくできないので、暑さもあいまって、むおっと包み込まれた感じには、なかなか慣れることができずにいた。便利より、安全より、清潔で健康的な環境のほうが重要である。そんな自分の価値基準がわかって面白い。
その日は、昼頃から部屋で原稿を書こうと思ったのだが、いっこうに集中できず、ガンジス川を眺めながらうだうだしていた。東京の真夏の気温よりちょっと高いくらいだろうか。閉め切った部屋でクーラーもない。普通なら暑くてたまらないはずなのに、おかしい。だんだん、寒く感じてくるのだ。毛布にくるまるが、寒気はどんどん増してくる。これは風邪の前兆だと予感し、早めの対策で寝ることにした。
夕方、目が覚めても、あいかわらず寒気は続いている。でもこの時はまだ余裕があって、夕食時、同行している旅仲間に「風邪っぽいんだよねー」と心配かけないように笑って伝えて、フルーツジュースだけを摂ってまたすぐに寝た。
いよいよ、その夜中である。急激な寒気と体中の痛み、下痢の信号で、目が覚めた。「なんだこれ!」異常事態にトイレに立ち上がろうとするが、立ちくらみのような状況で、上手く体をコントロールできない。夜中にトイレに起きてもいいように、部屋の電気はつけっぱなしで寝ていたので、その辺は助かった。
這うような格好でトイレにたどりつき、座る。がたがた震えるほど寒気がするのに、汗が噴き出してくる。確かに目を開けているのだが、目の前は緑がかったモノクロで、アナログテレビの砂嵐やカメラのフラッシュも混じってくる。体に力も入らないし、平衡感覚がきかなくなってくる。こんなヤバい状況、初めてだ。インフルエンザで40度の高熱が出た症状に似ているが、あのときは寝る場所とトイレと飲み水があればとりあえず安心していられたなあとか、それでもこの時はまだ考える余裕があった。原因はわからない。食べものにあたったのか。洪水の中をさまよった際に何かバイ菌をもらったのか。
トイレに座りながらも、ぐらぐら揺れている。だんだん意識が遠のいていく。「え…、まずい、まずい、まずい…」死という言葉が頭をよぎる。朦朧とした中で、顎の先からポタポタとしたたり落ちる汗を感じ、集中する。気を確かに持て。落ち着け。どうやってこの難局を乗り越える?
集中しても、体のぐらつきを制御できない。ふっと一瞬、気絶をしてしまった。「ガゴンッ!」トイレの床のコンクリートに肩と頭を打った音がした。痛さはまったく感じない。それなのに、床のひんやりとした温度は感じた。これはもはや一人ではどうにもできない、助けを呼ばないと。でも声が出ない。ならば音を出せ。床を叩いても、コンクリートでは、「ペチペチ…」しか鳴らない。これじゃ誰も気づくわけがない。体も動かない。iPhoneにも届かない。ここはバラナシだ。救急車はあるんだろうか。現在、だいたい夜中の2時と予想。きっと朝9時になれば、仲間が様子を見に来てくれるだろう。寒くて体中が痛くて今にも意識が消え入りそうなのに、あと7時間も…。それまでぼくの体はもつのだろうか。救助までの先の長さに弱気になる。時間というのは、伸び縮みするもので、楽しい映画を観ている2時間はあっという間だが、火の上であぶられている1分は永遠にも感じるものだ。
あと7時間…。無理かもしれない…。そう思った瞬間、「ブーン…」という小さな音とともに目の前から光がなくなった。死んだのか。ぼくは死んでしまったのか。しかし、汗だか涙だか、水分がしたたる感覚がある。死んでいない。
そうか、いつもの停電だ。停電になると部屋は一点たりとも光のない漆黒の闇になる。希望を失いそうになっているぼくを象徴しているようだ。夜中の停電は復旧が遅れる。朝日が出るまで光は見えないだろう。光があるかないかは危機的状況にある人間の精神に大きな影響を与えるものだ。
どうしてぼくはインドでひとり倒れているんだ?「Before I die. I want to… 」死ぬ前にやりたいことはなんだろう。「やりたいことが無くなったとき、死が訪れる」と聞いたことがある。絶望しないこと。これが生死を分けることを、アウシュビッツ強制収容所のドキュメント『夜と霧』を何度も読んで学んでいた。人間は思っている以上に強いもの。どんなに劣悪な環境でも耐えることができる。栄養が足りなくても、自分の体内でつくり生きることができる。最後まで生き残ったものたちは、どんな人たちだったか。それは、力が強い人でもなく、健康で丈夫な人でもなかった。「生きつづけなければいけない理由があるか?」その問いに答えられたものだけが、生き残れたという。
「なぜ生きるのか」これは、なにも大げさな話ではない。たとえば、自分には帰りを待ってる人がいる。やりかけの研究がある。もう一度見たい景色がある。子どもの世話をしなければ…。どんなものでもいい。自分がこの世にいなければならない理由がある。そう感じている人のみが、絶望せずにいることができた。終わりのない苦痛を乗り越えることができた。ぼくが生き続けなければならない理由は…。もちろん、ある。それは…。「ハア、ハア…」自分のうめき声が、遠くに聞こえるようになり、ついに完全に意識を失ってしまった。
「キー、キキッ、ドンドン!」外で野生の猿たちの騒ぐ声がする。こちらでは毎朝恒例の日常だ。目を開けると光がさしていた。ぼくは生きてるのか? 手が動く。意識が戻ったのだ。よかった生きてる。いくぶん体が楽になっている。それでもフラフラで、30分くらいかけてゆっくりベッドまでいき倒れ込み、それから4日間寝たきり状態が続くことになった。けれど、きっと峠は越えたのだろう。死の恐怖はない。あとは過去にも経験のある高熱と下痢というだけの話である。「寝れば治る」が信条なので病院にはいかず、厚手の毛布で熱を出し、フルーツと水をたっぷり摂って、毒素を出し切る。この自然治癒方法でいくことにした。下手に薬で熱を下げない方がいい。これは書籍『風邪の効用』で学んだ、必勝パターンである。過去に30日間の断食を経験しているぼくは、フルーツと水さえあれば死なないことを身を以て知っている。とくに不安になることはない。寝たきりで部屋から出られなくても、峠を越えたであろうことに心は軽くなっていた。
「なぜ生きるのか。お前が生き続けなければならない理由を答えよ」あの夜、たしかに死神と対峙し、問われていた。あなたなら何と答えるだろうか。ぼくにはこの生まれたばかりのオーディナリーがあった。この子が育つのを見届けずに、いま死ぬわけにはいかないのです。そう答えたのだった。
旅人の望むものが手に入るという聖地、バラナシ。それは本当なのかもしれない。「生きること」を体感するためにこの地を訪れたぼくの望みを、早くも叶えてくれた形となった。そんな話を、病床でぼくは旅仲間に笑って語っていた。その後、さらなる危機が訪れるとも知らずに…。(つづく)
※編集部注
倒れた際の実際の状況は、実情を克明に描写すると、グロテスクになってしまうので、きれいめに伝えるように修正しました。イメージ写真もショッキングな部分は避け、比較的目に優しいものを
選んで掲載しています。いろんな方が閲覧する可能性のあるWEBページゆえの配慮です。
Photo by M.KAWANISHI(上), N.KUMAGAI(中)