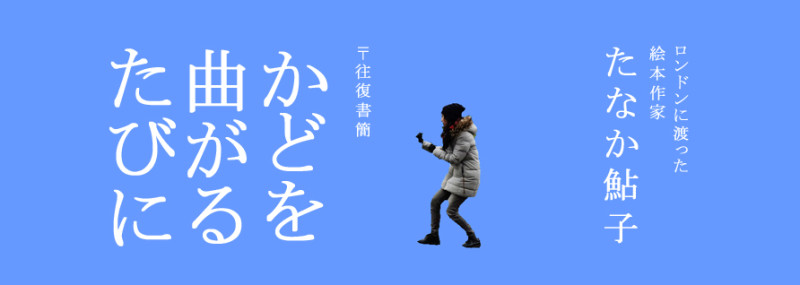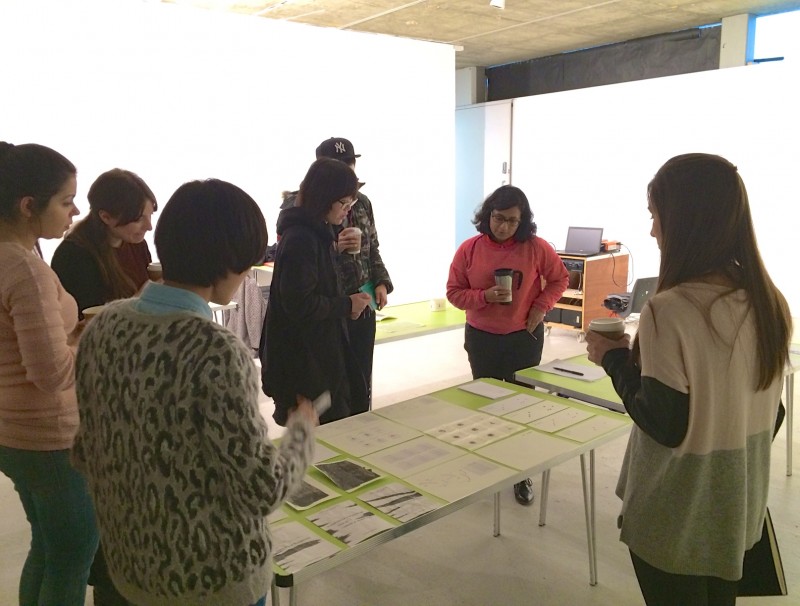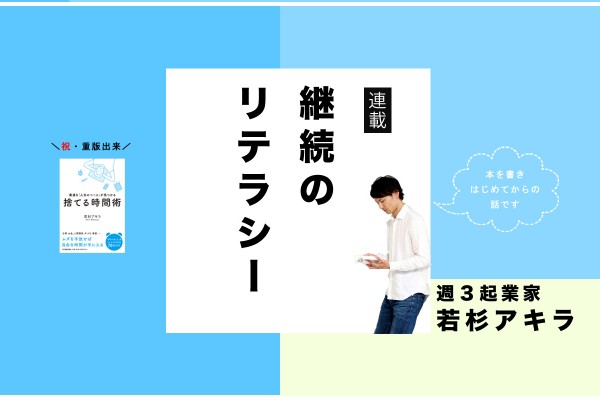抽象的概念と現実の間に橋をかけようとする作業は、クリエイティブな考え方やデザイン思考の大きな助けになります。ではどうやって橋を架けるのか。答えはひとつ、「つながると思い込むこと」世界に存在するものは、必ずどこかでつながっているのです。
往復書簡 ロンドンでの挑戦と創作をめぐる対話
第4通目 「新しい自分になるための学びについて」 (後半)
前回のお便りは真冬のクリスマスの時期でしたが、いよいよ3月。こちら東京はまだまだ寒く、早くあたたかくなって欲しいものです。その後、年越しも経て、いかがお過ごしですか? 日本でさまざまなアートワークを積み上げてきた鮎子さんでも、そちらロンドンの大学院の課題がなかなか手強いという話。大変そうな中にも、充実した様子がうかがえます。何をやろうにも「なぜ?」と聞かれると。ただ「なんとなく好きだから」では済まされない、論理的、コンセプチュアル美術教育体験とはどんなものなのでしょう? 深井次郎(ORDINARY発行人)2015年3月08日 |
|
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ![]()
深井さん、こんにちは。3月に入ってから、空がぐんと明るくなりました。日本では冬好きなんですが、どよーんとした「ロンドンの冬」にはさすがに参ってしまい、今は毎日春の息吹を感じられるのが心底嬉しいです。最近ではひなたを見つけるとわざわざそちらに行ってしばらく太陽光を浴びます。紫外線云々よりセロトニン不足が怖い…。
.
年末から年明けにかけて、日本から友人夫婦がはるばる訪ねてきてくれました。一緒に旅行したり、年越しビールを飲んだり、ものすごく楽しい時間を過ごしました。なんでしょうね、本当に友人っていうのはありがたいものです。
彼女とは大学時代からの友人で、当時ロンドンに一緒に旅行したこともあるのですが、十数年経ってまた、同じ場所で会ってぎゃあぎゃあバカ騒ぎができる。たくさんの幸運の積み重なりと、たくさんの支えがあって実現することだと心底思います。いやほんと、ありがたい。合掌(笑)!
私の日常はというと、相変わらず大学院のリサーチと日本から頂く仕事に交互に取り組む毎日。とにかく飛ぶように時間が過ぎていく、という実感です。
昨年の10月に、グラフィックデザイン・コミュニケーション科に入学した事はお話しましたが、私がこちらで向き合っている「グラフィックデザイン」が、日本で思っていたものとずいぶん違うので驚いています。
「グラフィックデザイン」というと、主に出版(本や新聞)と広告(ポスターやコマーシャルなど)のビジュアルを作るデザイナーを思い浮かべる方が多いと思います。必然的に、出版界や広告代理店など、産業との結びつきが強いイメージがあるでしょう。
もちろんこちらでも業界とのつながりは重視しますし、企業のコラボなどを視野に入れるプロジェクトも数多くありますが、始まりは自分。デザインを単なる仕事ではなく、ライフスタイルとして捉えているデザイナーが多いように思います。日常の仕事と別に独自のプロジェクトを持つ、というスタイルです。
今自分が居るのが大学院だから、ということもあるでしょう。すでにプロとしてのスキルを持ち、今後のキャリアと生き方を考える段階に入った人間のために開かれた環境だともいえると思います。
「抽象的な概念」と「目の前にある現実」に
橋をかける作業
最近、いろいろなギャラリーに出掛ます。デザインレクチャーの聴講も増えました。自身のプロジェクトのプレゼンなども続いているのですが、そこでもやはりよく感じるのは、日本とこちらのものの考え方、組み立て方の違いです。…もしかしたら今の世代は違うのかもしれませんが、少なくとも私の世代では体験しなかった理論作りが中心です。
前回も少し触れましたが、こちらではあらゆる行動、感覚に対して「理由」を求められます。「理由なんてないんだよ! 」では通用しない。物事の後ろには必ず理由がある、という考え方が当たり前のように存在しています。
え、それ説明しなきゃダメ? そんなことどうでもいいじゃん… と思いながら必死で考えていると、はっとそこに小さな理由を見つける瞬間がある。これまで遠くにあったものが、突然身近に感じられたり、前からそれを知っていたような気持ちになったりします。
日本ではどちらかというと、概念と現実が割とはっきり分かれていますよね。例えばヘンな例ですけど、仏教思想と新幹線の技術の間にパッとつながりを感じる人は少ないと思います(笑)。でも、こちらでは真顔でその類似性を論じたりする。いやもう、ホントビックリするくらい真顔です。
このような、抽象的概念と現実の間に橋をかけようとする作業は、クリエイティブな考え方やデザイン思考の大きな助けになります。特に私のように、「やりたいこと、伝えたいことがボンヤリあるんだけれど、どうしたら良いかわからない」と思っていた人間にとっては、もやが少しずつ晴れていくような、やりがいのあるプロセスに感じられます。
世界に存在するものは
必ずどこかでつながっている
さて、ではどうやって橋を架けるのか。答えはひとつ、「つながると思い込むこと」です。
ええーっ。なんておおざっぱな… とは私も始め思いましたが、実際この一言に尽きるのです。私はこちらにきて、さっさと諦めないクセをつけるようになりました。こちらの人は、それはもうすばらしく粘っこいので。
「世界に存在するものは、必ずどこかでつながっている」と、環境問題や政治問題に取り組んでいるデザイナーのデビッドがレクチャーで言っていたのがとても印象的だったのですが、一見、まったく関係ないように見える二つのものが、実はどこかでつながっていたりするものなのです。
たとえば先ほどの「仏教思想と新幹線の技術」だったら。私なら多分、まず… 新幹線の持つ精確さ、緻密さから日本のものづくりの精神を連想します。ものづくり精神のルーツとして、「物」=自然に神が宿るというアニミズムや神道、またはミニマリズム的な考えとしての禅思想が浮かんでくれば、両者の比較とか類似性を通じて、仏教思想への道すじをなんとなく思い浮かべることができたり。もちろんこのルートでなくても、ビジネスとか科学だとか、他にも無数につながる道すじは見つかるはずです。
どうしてもうまくつながらない場合は、急ぎすぎている可能性があります。二つか三つ、段階をはしょっているのかもしれません。そういう時は、少し前の段階に戻って可能性を考え直す。すると、また別のつながり方が見えてきます。
このインスピレーションを裏付けるために、今度は自分の好きなアプローチを選びます。歴史が好きなら歴史学、または心理学、民俗学などなど、好きな道具を用いて始めの課題を肉付けしていくプロセスです。
…と、わかったようなことを言っていますが、こういうのは全部学校での鬼教官による叱責… じゃなくて指導や、前回も紹介しました、頼もしいクラスメイトのアドバイスを通して少しずーつ身につけようとしていることだったりします。でも、これまで孤立していた個々の知識が、何かとつなげることで生き物のようになる瞬間を体験するのはとても楽しいことです。
出発点はあくまでも自分なので、自分の体験や考えを徹底的に見つめるところから始めて、過去の研究やアーティストのプロジェクトなどからもメッセージを拾いつつ、社会やある一定のコミュニティに対する問いかけへとつなげていく。
頭がクタクタになるくらいこういうことを続けていて気づいたことなのですが、こういう考え方、人間としての存在の仕方が、西洋思想の中心にあるんだなと。選択をして、自分がなぜその選択をしたのか、はっきりした理由を見つけて納得することで、自分自身を昨日よりもう少しよく知ることができる。外部からいろいろな影響を受けつつも、なんといっても自らこの人生を選んだのだ… という実感を持って、多分生きている。これがボトムアップで民主主義を突き上げてきた国の基礎にある考え方なのかもしれないな… と、そう思いました。
今は結果よりもプロセスが大切
とはいえ、もちろん毎日毎日そんなにビシビシやりがいを感じながら生きているわけではありません(笑)。正直いって、ほぼ毎日グダグダと、あっち行ったりこっち行ったり、「私ホントこんなことしてて良いのか?」と思う時間の方が長いといえば長いです。それに、多分大学院生なら誰しも持つ感覚だと思うのですが、「はて、今やってることって、欠片でも世の中の役にたつのだろうか?」と、心底やる気のなくなる瞬間の訪れることも、一度や二度ではありません。
むしろ全然役に立たないであろうことはほぼ確実(はっヤバい、役に立つと信じなきゃいけないんだった)なのですが、とりあえず今、自分にとって大事なのは問題解決じゃない。
自分なりに問題を設定し、世の中を変える気持ちで取り組み、その上で考えるプロセスを体験すること。そうすれば社会に出た時、いろんな側面で応用が可能になると思うのです。私のようにフリーランスで、しかももう人生折り返しちゃってどれだけ社会にお返しできるのか疑問な人間も居るには居ますが、少なくともきっと今後、何かしら自分自身の心を救う助けになってくれると思います。
とはいえ、デザイン科ですから、最後は見た目で勝負(笑)。
再来週にはインターリアム・ショー(中間発表)という展覧会があり、目下私たちはその準備に追われています。
こういうクリエイティブ系のコワイところは、いくら理屈が立派でも、最後はぽーんとカッコイイ見た目にやられてしまうところ。理屈がないと薄っぺらいものになりますが、理屈だけ立派でもダメ。どんどん作って、どんどん隠れている自分のダメなところをさらけ出さないといけないわけです。
私はとりあえず得意な道具(絵)をなるべく使わないで表現してみたいと思い、あれやこれやと試行錯誤中です。
ということで、またいろいろご報告させてもらえたら思います!(了)
ーーー
ーーー
(次回をお楽しみに! )
| 連載「かどを曲がるたびに」とは
「こちらロンドンは、角を曲がるたびに刺激があふれています」絵本作家たなか鮎子さんは2013年冬、東京からアートマーケットの中心ロンドンに活動拠点を移しました。目的は、世界中にもっと作品を届けるため。42歳からロンドン芸術大学大学院(著名アーティストやデザイナー、クリエイターを多く輩出している)で学んだり、ファイティングポーズをとりながらも、おそるおそる夢への足がかりをつかんでいく。そんな作家生活や考えていることをリポートします。「鮎子さん、まがり角の向こうには何が待っていましたか?」オーディナリー発行人、深井次郎からの質問にゆるゆると答えてくれる往復書簡エッセイ。 |
連載バックナンバー
第1通目 「ロンドンは文字を大切にしている街」(2014.3.5)
第2通目 「創作がはかどる環境とは」(2014.9.29)
第3通目 「新しい自分になるための学びについて」 (前半)」(2014.12.20)
特別インタビュー
PEOPLE 05 たなか鮎子「きのう読んだ物語を話すような社会に」(2013.12.31)