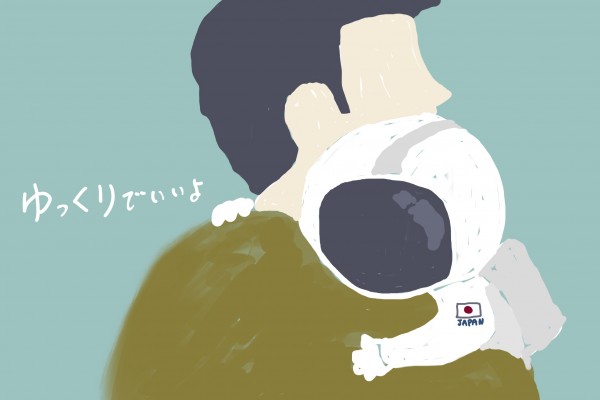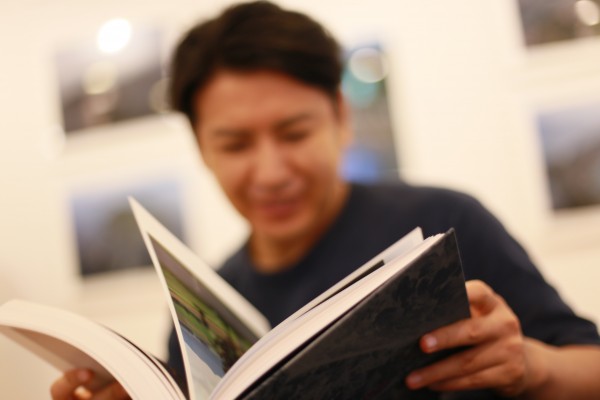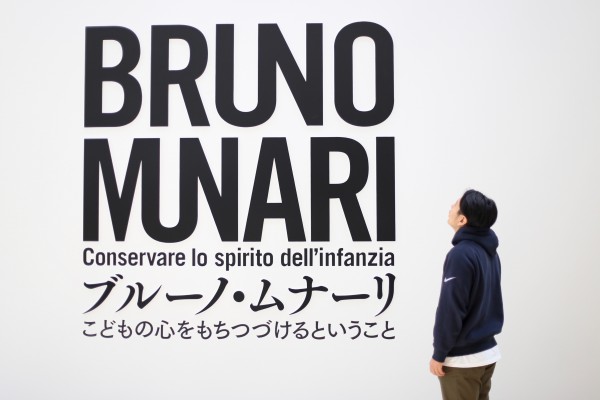「みんないい YO! それぞれ素晴らしい YO!」
チームを破門にされた黒須くん
理由は「活躍しすぎて」
.
好きなことをやって生きようかな。そう決めても、なかなかうまくいかない理由のひとつは、自分ひとりではできないものもあるからです。
ぼくは週末にバスケをやっています。絵を描くとか、ボーリングとかなら自分ひとりでもできますが、バスケは仲間をつくらないとできません。そうなると、自分に合ったコミュニティーにめぐり会うか、探してみてどこにもなかったら自分でつくるか、ということをしなければ。そのひと苦労があるのです。
「はじめまして。あの、いまプレーできるチームを探してまして…」
先日、黒須と名乗る若者(20代前半)がぼくらのサークルの練習にやってきました。ゲームをすると、すごく上手い。大学でも体育会で本気でやってたレベルです。
「黒須くん、上手いねー。今までやってたチームがなくなっちゃったとか? よくあるよね」
社会人のサークルはゆるいので、チームが自然消滅することはよくあります。まとめ役のリーダーが転勤になってしまったり、子どもが生まれたり仕事で忙しくなってしまうと、人数が集まらなくなって、そこで新人募集がうまくいかないとゲームができないので消滅してしまう。3年続かないサークルが8割以上だと聞きます。黒須くんもそういう事情なのかなと思ったら、
「いや、実はリーダーに嫌われまして… 破門にされました…」
「は、破門?」
パッと見、人間性に問題があるようにも見えないし、挨拶もできるハンサム好青年です。
「どうして、なんか悪いことしたの?」
「じ、実は、試合で活躍しちゃったのがいけなかったみたいで…」
「なにそれ面白い、どういうこと?」
聞くと、黒須くんはチームのリーダーとポジションが被っていて、しかもリーダーよりも上手かったようなのです。だからリーダーにとっては、彼が試合で活躍して自分よりも目立ってチヤホヤされてしまったのが気に入らなかった。と、そういうことみたいです。
そして、辞めさせられ方も、リーダーからこんな電話がかかってきたそうです。
「あのさ、チームのみんながお前のこと嫌いだって言ってるんだよね。頼むから辞めてくれる?」
みんなが、という表現が、器の小ささを物語ってます。はっきり言おうよ、と。「俺はお前のことが気に食わない」なら、まだ清いです。
「いやー、小さいねぇー」
その場にいるみんな一同、笑って打ち解けました。でも、彼は新しいぼくらのサークルに来るようになってからも、よほどトラウマだったのでしょう。自分でシュートに行ける場面でもアシストに徹したり、上手さをひけらかさないように、存在を目立たせないように、気を使ってプレーしていました。
「もっとノビノビ勝負すればいいのに。できるでしょ?」
「い、いや、大丈夫っす」
.
競争型リーダーと共生型リーダー
あなたなら、どちらを選びますか?
.
能力のある若者がのびのびできない組織って、どこにでもあるよなぁ。彼を見ながら思いました。先ほどの器の小さなリーダーを筆頭に、原因の多くがリーダーにあるのでしょう。
リーダーには2種類いて、競争と共生、どちらの精神性でそのリーダーが動いているのか。これが組織に大きく影響します。
競争型リーダーは、チームの部下とも競争してしまいます。「リーダーたるもの自分が常にNO.1であらなければならない」と思い込んでいるのです。スキルも一番、地位も一番、人望も一番ある。そういう「エースで部長で全員から崇拝されてます」という状態じゃないと許せない人です。お山の大将、猿山のボス的なスタンスです。
こういう競争型リーダーが上司だと、下は押さえつけられます。リーダーを超えることは絶対に許されません。黒須くんのように、上手すぎてリーダーのご機嫌を損ねて破門になるということがある。
ぼくは学生の頃、さまざまな経営者に会って、ぐったり疲れたりしながらこれに気づいていたので、20代も競争型リーダーの傘下には入らないようにくれぐれも注意してきました。もちろん自分が組織をつくるときも気をつけています。せっかくの若い才能を伸びずに枯らせてしまうからです。
外から見てる分には、競争型リーダーの組織もうまく機能しているように見えたりもします。けれど、中に入って初めて窮屈さに気づく。そういうことが多かったです。
若者の行動パターンとして、綺麗な花に蝶が引き寄せられるように、カリスマに憧れるということはあります。そして、そのカリスマの近くで学びたいとその組織に入る。しかし、業界のドンとかカリスマと呼ばれるような人に限って、競争型リーダーが多いように感じます。
下の才能をいかに開花させるかよりも、自分の都合の良いように下をどう使うかというパワーがものすごい。「短期間の修行」と割り切ってなら、お山の大将の下でも学ぶことはありますが、5年も10年も長く傘下にいると、ただのイエスマンというか骨抜きになってしまいます。そんな環境ではリーダーの顔色が最優先なので、自分のやりたいことなど考える余裕もないし、好きなことに気づくセンサーも鈍る。自分の意志が放電してなくなってしまうのです。
競争型リーダーを避けるために
見分け方、3つのポイント
.
ポイント1:辛口でダメ出しをすることが多いかどうか
彼らは部下が成功しても「すごいね、よくできたね」とほめて伸ばすということがありません。常に「まだまだたいしたことないね。そのくらいはだれでもできる」と批判して自信を失くさせます。上から目線で、謝らない。譲らない。勝つまでディベートする。見栄っ張りで、自分優先、自己顕示欲が強いという傾向があります。「自分以外は全員バカ」的な見下した態度。
外の権力者には営業的にお世辞を言うこともありますが、身内には辛辣です。「うちの部下は使えないのばかりで、困っちゃいますよ」と身内をけなす傾向があります。本当は、部下が使えない状態でいてもらったほうが、自分にとって都合がいい。成長しそうになったら、わざと押さえつけているのです。(リーダー自身は無意識でやってることが多い)成長して自分よりできるようになってしまったら、ボス猿の座が危ぶまれるから。
世の中のリーダーには2種類いて、「すごく見られたい人」と「本当にすごい人」がいます。前者が競争型、後者が共生型。次世代のリーダーたちが育つのは、たいてい共生型リーダーの下からです。
ポイント2:会った後にエネルギーを吸われた気がするかどうか
「なんだかぐったり疲れたなぁ」競争型リーダーは他人をコントロール、支配たがるので彼らと接した後は疲れます。自慢して尊敬させようとしたり、機嫌を悪くして気を使わせたり、彼らはまわりからエネルギーを吸い取って、それで元気になっているのです。とにかく機嫌が悪い人からは、離れたほうがいい。ワンマン社長で、社長だけ常に元気いっぱいで、まわりは全員ぐったりという会社をあなたも見たことがあるのでは。
競争型リーダーは不自然なほど元気にあふれているから、一緒にいると感化されてこちらも元気になった気がする時もあるのです。でもそれはカフェインとかチョコレートとかの刺激物と一緒で、一瞬はシャキっとするのですが、その分あとでリバウンドがきて余計にぐったりします。ちゃんとした栄養のある野菜とか果物だったら、おいしいしリバウンドもありませんね。会った後、ぐったりしたら注意。
ポイント3: 下からたくさん優秀な才能が育っているかどうか
リーダーの部下だった人物を見てみます。すると、ボス猿の下で育ったのは小粒ばかりということがよくあります。そしてまわりが自由にイキイキ笑っているか。疲弊している感じだと危ない。離れないと、あなたの開花するはずだった才能もつぶされてしまいます。新たな挑戦をしようにも「まだ早い。無能なお前にできるわけがない」とダメな理由を押しつけ自信の芽を折られます。
これら3つのポイントをみて、危なそうだと思ったら、無言で離れます。リーダーを批判することはありません。そういう人がいてもいい。合わない人とは、無言で静かに離れるのが平和で健康的です。
まわりの才能が開花していく
共生型リーダーとはどんな人物なのか
.
先ほどの競争型リーダーの反対を考えれば、共生型リーダーがどんな人物か分かります。共生型リーダーの下からは、新しい才能が育って、四方八方に散らばって各分野で活躍しています。共生型リーダーは自分自身も成長するけど、まわりの人も盛り立てます。「大丈夫! キミならできるよ、その調子」とその人の長所を気づかせて伸ばしていくことができます。部下が自分を超えていく姿も「いやー、頼もしいね」とまるで自分の成功のように喜びます。
自分自身の自慢はしませんが、自分のまわりの人の素晴らしさについては自慢することもあります。部下のことを、「彼は本当に素晴らしくて、天才じゃないかと思ってるんですよ」とか自慢する。
「自分が気持ちよければいい」のが競争型だとすれば、「自分も、まわりも、社会もみんな良くなればいい」と考えるのが共生型です。本来すべての人がもっているそれぞれの才能を、すべて開花させることができれば、どんなに素晴らしい社会になるでしょう。そうなれば自分も嬉しいのです。
自分が競争型リーダーに陥らないようにするにはどうするか。まず、この観念、「リーダーとは全てにおいてNO.1でなければならない」という思い込みから自由になることなのでしょう。「みんな頑張ってるねぇ、すごいねぇ」と笑って応援して優しく見守れるかどうかです。
共生型の組織がサステナブルである理由
.
永続する組織の条件は、自分よりも有能な人をチームメイトにできるかです。「上の代」より有能な「下の代」を採用できるかどうか。「この人は自分よりもすごい」と思える人をずっと採用し続けることができたら、組織はどんどん強くなるはずです。
でも、競争型リーダーの組織は、競争原理で動いているので、自分よりも小粒な人を採用します(これは無意識に)。そしてその部下も自分よりも小粒な人を部下に採用するという連鎖で組織はどんどん弱くなります。良く言われる「組織はリーダーのレベル以上には成長しない」という状態になるわけです。
特に「将来独立して自分がリーダーとしてやっていきたい人」とか、「自分の才能をのびのびと開花させたい若者」は、競争型リーダーの下に長くいすぎないほうがいい。「カリスマは綺麗な花みたいなもので、遠くから見てる分にはカッコいいけど、近づきすぎると毒だな」と、それを学べただけで十分いた意味があります。
共生型リーダーは、それぞれが120%の力が出せるように、まわりの才能を開花させることに心をくだきます。みんなの才能が開花して成長していくと、リーダーを超えて独立して散り散りになり活躍していきます。そんなに独立していってしまったら一瞬、「チームに誰もいなくなってしまうのではないか」と心配する人もいるのですが、そうはなりません。
次世代のリーダーたちを輩出した場所として、評判を聞きつけてまた新しい才能がどんどん入ってきてチームに加わり、良い循環が起きます。全員が共生、繁栄していく。その共生モデルの方が、あなたが好きなことを長く続けるには良い、サステナブルだと思いませんか。
いま、競争型リーダーの下で
押さえつけられている人たちへ
.
競争型リーダーの末路は、残念ながら明るいものではありません。リーダー自身が衰えたり、ストレスで体を壊したらジエンド。ボス猿は下克上されるか、ワンマンで下が育ってないので組織ごとつぶれます。
では現在、会社で競争型リーダーの下にいる人はどうしたらいいでしょうか。まず、「そうか、自分はいま競争型リーダーの下にいるのか」と自覚した時点で少し楽になります。冷静になって、自分を大切にして、批判されても流せばいいし、あなたのコントロールは効きませんよ、とバリアを張ってエネルギーを吸い取られないようにすること。どうしても離れられない場合は、バリアしかありません。
会社の場合は、3年も我慢すればその上司は異動になるでしょうから、それまで待てる人は待つというのも手です。リーダーがオーナーの場合は待っても変わらないので、学ぶべきことを学んだらすぐに出た方がいいでしょう。
競争型リーダーの下にハマって出られなくなる部下の特徴としては、自分に厳しいタイプの人が多いです。褒められると居心地が悪く感じ、逆に「ダメ出しをされた方が弱点を克服できて成長できる」と信じているタイプの人いますね。彼らは、ハマりやすいです。ストイックなのはいいのですが、短所を克服するより、長所を伸ばした方が本当は成長できるし、社会のためになります。(なぜかという理由は長くなっちゃったのでまたの機会に話しますね)
.
以上、好きなことを末永く続けるために、そしてあなたの才能を開花させるためには、共生型リーダーのいるコミュニティーに身を置くのがいいよ、というお話でした。
サイズの小さいシャツは、どんなにそのデザインやブランドが気に入っても、着ることができません。それと同様に、器の小さなリーダーのいるチームにはどんなにバスケが好きでも、居続けることはできないのです。
黒須くん、大変だったね。ようこそ。新しいチームで、のびのびと楽しみましょう。