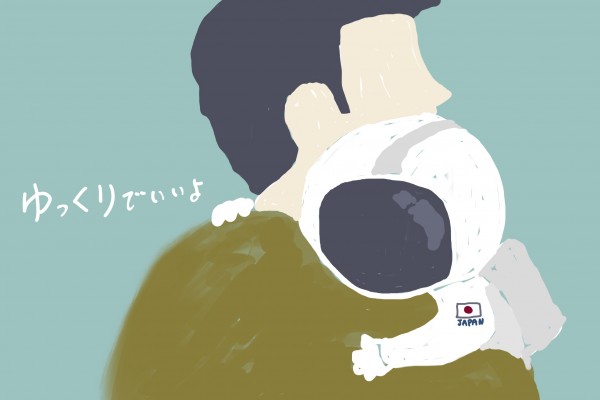貧しいものも富めるものも
ガンジス川と共に生きる
【インド旅篇】
ぼくらが物乞いに
どう対応したか
———-
物乞いについては重い話だけど、このことに触れないわけにはいかないでしょう。歩いていると、物乞いはわらわらとやってくる。歩けるものは、寄ってきて「1ルピー」と切なそうな顔をしてせがむ。歩けないものは、刺さる視線と仕草で訴えてくる。お札を数えるような、指をすりあわせる仕草をするものもいるし、ご飯を食べる仕草をしてアピールするものもいる。手をつかんで歩みを阻んでくるものもいる。触れられた時の、細くて冷たい感触と伝わってくる悲しみのようなものに感情をゆさぶられます。1ルピーは日本円で2円くらいですから、こちらとしては「このくらいで喜んでくれるのなら」とついあげてしまいたくなります。
しかし、宿のスタッフたちとこの物乞い問題について話しあって、わかったことがあります。実は、物乞いもビジネスで、悪い組織が物乞いからお金を吸い上げているケースが多いとのこと。何割の金額が吸い上げるかはわからないけど、彼らにお金を渡すことが社会にとって良いことかは一概にそうとも言い切れない、複雑な問題のようなのです。
子どもをつかって同情させたり、足がないことで同情させたり、そういう工夫をしている。物乞いという職業なのです。残酷なのは、わざと障害をつくる人たちもいるということだ。親が自分の子どもの足を切り落としてしまう。生きていくのに不自由にはなるが、そうしたほうが生涯で考えたときに稼げるからと、そうする人も多い。そしてその子がいずれ親になり、自分の子の足を、というように、世代間で連鎖していくとのこと。
悪の組織にお金が流れるといっても、彼らがお腹がすいてるのは間違いない。何かはしてあげたいと考えて、スタッフたちに相談したら、今のところ一番いい施しは、「ご飯をおごる」ということにいきついた。現物支給なら、悪に加担せず、本人の力になることができる。「いま何が食べたい?」と聞いて、パッと出てくる人には、それをおごった。中には、「いや、食べ物ではなくお金をくれ」と言い張るものもいた。「バナナはどう?」と聞くと「いや、バナナには飽きたから、お金を」と言われたこともある。それは完全に仕事としての物乞いだから、心を鬼にして相手にしなかった。
物乞いの子どもたちの写真を撮った
車にはクーラーがないので、暑い。基本的に窓を開けて走っている。渋滞などで止まった時には、ふっと外から物乞いの手が伸びてきて冷やっとする。それが心臓に悪いので、スピードが落ちてきたら、警戒して窓をしめていた。
車で隣町にいくとき、15分ほど踏切で待っていた。15分も窓を閉めっぱなしでは暑くてたまらない。さすがに、開けてしまう。それを見越してだろうか、子どもたちに車が囲まれた。この踏切はいい仕事場なのだろう。子どもたちなので、威圧感はない。見ると髪型も整ってるし、わりといい服も着てて元気だ。この子たちも、仕事だろう。お腹が減っている演技をしてくる。「ダメだよ」と断り続けていたら、いよいよ諦めて演技モードが解けた。いつもの元気で無邪気な子どもの遊びモードになった。彼の笑顔の写真を撮って、液晶画面を見せると、喜んで歓声をあげる。「ぼくの弟も撮ってよ」撮ってあげて見せると嬉しそうに笑う。インドでは、写真を撮ってあげると喜ぶ人が多い。カメラを持っていると「撮ってくれよ」と寄ってくる人もいる。撮られて満足なのだ。
「写真撮ってもらえますか?」日本でこう声をかけられたら、普通はその人のカメラで撮ってあげることだ。でもこちらでは、そうではない。ぼくらのカメラで撮ってあげる。で、彼らは撮られただけで満足なのだ。自分の存在を、誰かの記憶に残せたことが嬉しいのかもしれないのかもしれない。写真を撮ってあげるだけで喜ばれるなら、それはどんどん撮ってあげたい。踏切で待っている15分間、撮影会をした。笑い声のあふれる15分だった。
(約1582字)