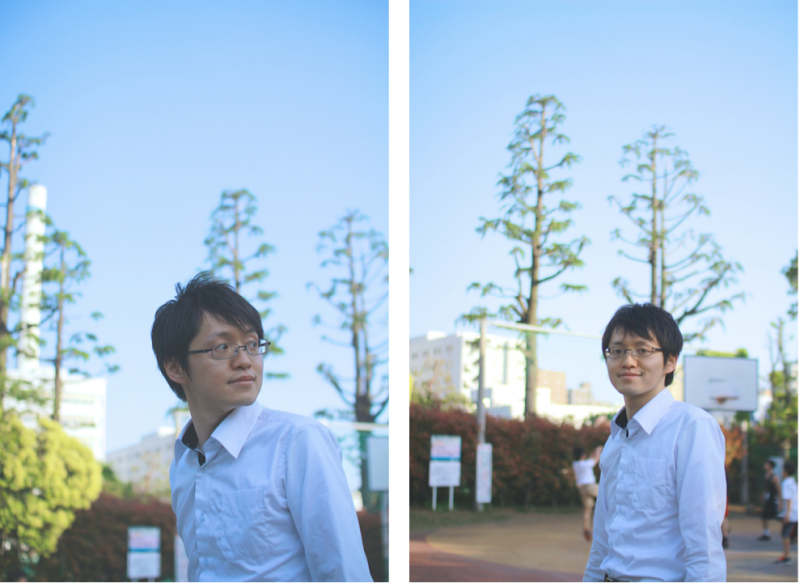望んだ形ではないかもしれないけれど、“ヒーロー”になる夢は捨てていない
第3話 伊藤 悠さんの場合
今の自分に耐えられなかったから
—
伊藤悠さんは現在、震災復興関連の団体で働いている。落ち着いた、知的な印象とは裏腹にずっと理想とのギャップに鬱屈しながら社会人人生を送ってきたという。“ここではないどこか” を追い求めて彷徨ってしまう現代に多くみられる若者として、もがき傷つきながら進んできた道のりを、正直に、カッコつけることなく語っていただいた。
—
ーーー
ーーー
しっくりこない20代
大学4年生の時、働くことの意味がわからなくなり就職活動をやめた。たまたま選考を受けていたベンチャー企業のインターンに誘われ、卒業後そのまま就職しようと考えていたが、担当事業中止のため仕事がなくなってしまう。結局、内定を取っていた人材サービスの株式会社インテリジェンスに入社する。配属は転職活動を支援する部署。働くイメージを持てずになりゆきで入社した伊藤さんが転職支援に携わるとは皮肉な話である。更にキャリアアドバイザーとして、毎月50人近い転職志望者と会い続ける業務は、当時会話が苦手だったという伊藤さんには厳しい試練だった。
最初から大きな違和感を抱えていた仕事にモチベーションは上がらず、充分な成果を出すこともできかった。入社3年目にその会社を去るときまで仕事はずっと苦しいものだった。
ーーー
在職中に偶然参加したイベントで、2社目の勤務先となる環境ビジネスの会社を知る。「この会社こそ自分が求めていた居場所だ」と思い込み、担当者が根負けするほどのアプローチを続けて採用が決まった。意中の企業で、熱望していた新規事業を任せられることになり、伊藤さんは情熱に溢れ、燃えたぎっていた。働くことに疑問を抱えたまま、なんとなく流れてきてしまった日々をようやく取り戻すことができるのだ。ここまでは素晴らしい展開だが、伊藤さんは4年後再び辞表を出すことになる。
3回目の転職、崖っぷち
伊藤さんには強い “ヒーロー願望” があると言う。みんなに一目置かれる、すごいと言われる存在となり、成功をおさめる。そんな、いわゆる中二病を引きずった社会人だった。新しい企画、面白い事業の先頭で旗を振るのが自分の役割だと信じていた。そのときの心境を語る伊藤さんの目には奢りや自尊心はなく、まるで「ヒーローになって悪者を倒す!」と宣言する少年のように輝いていた。
2社目の会社で、純粋な情熱で自分の輝く場所を創りあげようと邁進していたが、担当していた新規事業が立ち行かなくなり、間接部門に異動となってしまった。そしてまた、「ここは自分のいるべき場所ではない」という思いが復活する。仕事への意欲は激減し、アウトプットの質も上がらない。またもや燻り続け、転職活動を開始するが8か月動きまわっても次の仕事は決まらなかった。
ーーー
前職の経験から、自分が「転職市場で価値が低い」人材であることは悟っていた。武器となるものが何もない自分。その事実に直面しながらも、転勤を伴う異動を打診されたタイミングで会社を辞めることを決めた。
それから2か月のブランクを経て、大学の友人が働いていた震災復興事業の事務局を手伝うことになり、2012年の夏、陸前高田へ向かう。これが2度目の転職となった。長野で生まれ育ち、大学、社会人と東京で暮らし、縁もゆかりもない東北の港町で働く。その決断は、「何もない自分」を打破するためであった。
そして津波の被害を受け、ボロボロになった町で伊藤さんはとうとう自分自身と向き合わなくてはいけない状況に追い込まれる。
ーーー
30歳にして気づく
やるべきことは、ちゃんとやる
社会人になって7年半が過ぎ、伊藤さんは、大学の同級生の部下になった。給料は半分になった。入社早々、陸前高田の常駐スタッフになることが決まり、プレハブ倉庫を間借りしたオフィスで毎日一人で仕事をすることになった。一から十まで自分でやらねばならず、同級生だった上司は東京と行き来しながら、雑用ばかりを命じてくる。正直、初めから腐っていた。なぜこんなつまらない事務作業を自分がやらねばならないのか。
だが、いくつか失敗を重ね、とうとう理想には遠く及ばない現実の自分に向き合わねばならなくなった。自分しかスタッフがいないということは、「自分がやらなくては全てが止まる」ということだ。掃除をしなければ部屋は汚れる一方だし、紙がなくなれば補充しない限りコピーをとれない。
一番やりたくない、地味で誰にも褒められない“雑務”が降りかかってきた。津波で流され、ようやく復興に向かって進みかけている町で、将来の不安にかられ、再び逃げ出そうとした伊藤さんは、でも最後の糸を離さなかった。
「ここで逃げたら、きっと次も同じことの繰り返しだ」
社会人として瀬戸際に追い込まれ、ようやくその事実を認めた。もう自分を雇ってくれるようなところは見つからないだろう、あったとしてもきっとまた逃げる。ようやく、自分のために用意された舞台などないのだと悟った。そして、もうそれを追い求めていられるほど若くもないことを真摯に受け止める。自分が輝く場所は、自分でつくるしかないと気付いたのだ。
大器晩成型ヒーロー
それから伊藤さんは「つまらないこと」をひとつひとつこなしていった。掃除も買い出しもデスクワークも。それはかつて「自分の仕事ではない」と思っていた、新しくも面白くもない、ただ日常を維持するためだけの仕事だ。創造的でない仕事に時間を割いていると、まるで自分の創造性や強みがなくなってしまうような気がして怖かった。だが、社会は、誰かが誰もがやりたがらない仕事をして成り立っている。自分の周りで仕事がまわっていたのは、誰かがそれをやっていてくれていたからだということにようやく気が付いた。
一から人としてやるべきことをやって、自分を叩き直した伊藤さんは、今や立派な事務局員となり、組織にとってなくてはならない存在になっていた。更に次のステージを考えている。今度は逃げるのではない。もうすぐ請われて新しい組織に移る予定だ。スポットライトの当たる場所を追い続けても手に入らなかったけれど、今いる場所を磨き続けていたら、そこがいつの間にか輝く場所になっていた。伊藤さんが“美味しくない”と逃げていた仕事をやり続けて、つまらなくてカッコ悪い日々が評価されたのである。
ーーー
伊藤さんは、自分は“チャンスを待てない”人間だと言う。石の上に三年、潮目が変わるまで。そうやって虎視眈々と、来るかどうかわからないその瞬間を待つのが耐えられなかったと言う。
でもすべてをなくした瞬間こそ、そのチャンスだった。チャンスは輝いていない、いかにも、という顔で現れるわけではない。やりたくないと思って逃げていた、割に合わないこと、みんなのやりたがらないことをやって、自分自身を矯正した。今の姿は望んだ形ではないかもしれないけれど、“ヒーロー”になる夢は捨てていない。
ずいぶん遠回りをした。天才ではない、“持っている”人でもない。でも人間は自分が平凡だと気付いてからこそ人生が始まる。そして何もないことを自覚してから、何を獲得していくかを考えることができるのかもしれない。その痛みや傷を糧に、今日もヒーローになるその日に向かって走っている。
変わることを恥じない、恐れない
伊藤さんが怒涛の勢いで転がり落ちていった道のりの先には、何もない自分しかいなかった。そしてそれを認め、もう一度歩く決意をした。
30歳になると、そろそろ会社では部下を持ち、大きな仕事を任される、中堅と言われる年代である。役職がついた同級生の姿がちらつく中、伊藤さんは新入社員のような仕事をひとつひとつ、きちんとこなしていった。その決意が伊藤さんの道を徐々に軌道修正していく。10年かかった。だがその日々も無駄ではないと思う。伊藤さんは、多くの時間を無駄にした、何も学ぶことは無かったと言うけれど、最初の会社で、何百人もの人とコミュニケーションを取った経験は伊藤さんが人と接するスキルを格段に向上させた。それは被災地で、町の人たちと同じ目線で話すことができる点にも表れている。
ーーー
ーーー
私(むらかみ)自身2回会社を辞めた。だから伊藤さんの気持ちはよくわかった。誰もが、心の何処かで自分にもっと相応しい場所があるのではないかと思ってしまう。しかし転職経験者の多くが言うように、この世に「理想的な職場」など存在しないのだ。不満を数えるよりも、自分がどうすればよりよい環境に変えることができるか。それを考えたほうがずっと有意義な時間を過ごせると思っている。
伊藤さんの話で一番強く惹かれたのは、「変わる」ことを決意した強さだ。働き方、考え方を変えることは、それまでの自分を否定することでもある。それはとてもストレスの強い行為だと思うが、伊藤さんは変わることを決め、変わった。
会社を辞めるとき、ここで過ごした時間は何だったのだろうと考えてしまう。新しい仕事が面白い時、もっと早くここへ収まっていたらと後悔する。でもしばらくして、やっぱり今歩いているこの道の途中でしか、ここの場所には来られなかったのだと思い直すのだ。
華々しくはないが、現場から、当事者の目線に立って物事を作り出すという、伊藤さんの武器を活かせる仕事だ。出来ないことがたくさんあり、弱さもある、そんな立ち位置から働きかけられる伊藤さんの能力はこれからも活かされることだろう。
| プロフィール 伊藤 悠 (いとう ひさし) 1982年、長野県伊那市生まれ。地元と学校が嫌いで、大学から東京に出る。在学中はアメリカに半年留学し、国際関係学のゼミに入ったが、卒論は自分の地元の地域コミュニティの変容について書いた。大学卒業後、人材サービスの㈱インテリジェンス、環境ビジネスの企業勤務を経て、現在震災復興関連の団体で働く。仕事以外に、富山県の過疎地に都市の若者が通う活動を5年間続けている。地域と教育の変革がライフテーマ。「自分は間違った生き方をしてきてしまった」という思いがピークに達し、2度目の転職を考え彷徨っていた2012年初頭に自由大学の講義「自分の本をつくる方法」に参加する。当時の不安な気持ちは、STORY.JPの「30歳にしてバスケットボールを始めた理由」に語られている。 WEB:http://storys.jp/story/4719 |
ーー
ー(次回をお楽しみに。月一更新予定です)
連載バックナンバー
第1話 「できることを増やすため」 むらかみみさとの場合 (2014.4.20)
第2話 「旅に出るワクワクを抑えられないから」 小林圭子さんの場合(2014.4.30)