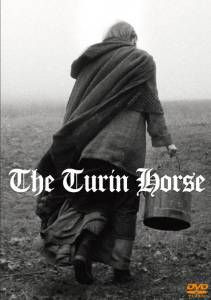ひとつの映像がいつまでも心に焼き付くことがあるだろう、その感覚が154分継続する強烈な濃度をもつ痺れるような映画なのだ。むかし映画学校の先生が言っていた「摂理があって撮る時は、映画の神様が手を貸してくれる。突然絶妙な角度で光が差したり、凪だったのがいい波が立ったり… 奇跡としか思わないことがフィルムに映せたら、その映画は神様に愛されているってことだ。」タル・ベーラの作品には必ずそういうシーンがある。
|
< 連載 > 映画ならたくさん観ている。多分1万本くらい。いろんなジャンルがあるけど、好きなのは大人の迷子が出てくる映画。主人公は大体どん底で、迷い、途方にくれている。SFXもスペクタクルもなし、魔法使いも宇宙人も海賊もなし。ひょっとしたらこれといったストーリーもなかったり。でも、こういう映画を見終わると、元気が湧いてくる。それは、トモダチと夜通し話した朝のように、クタクタだけど爽快、あの感覚と似ている。面倒だけど愛しい、そういう映画を語るエッセイです。 |
面倒な映画 11
「ニーチェの馬」
神に愛された仕事、マスターの流儀
苦く複雑な味わいゆえに客を選ぶ、何とも横柄な態度だ。しかしタル・ベーラというハンガリーの監督は、あからさまに選別する。看板から入りにくい「ニーチェの馬」。このタイトルにピンとくる人しか惹きつけられない映画だ。ドイツの哲学者ニーチェは鞭うたれる馬の首を抱いて発狂した。その後哲人は生涯を終える。その馬がどうなったか誰も知らない… というところから始まる映画だが、冒頭で眼を剥いて走る馬がその馬であるともないとも言いもしない。
ニーチェは以後ほぼ無関係。あとはただただコントのように絶えず暴風の吹き荒れる丘にかろうじて建つ廃屋のような家で暮らす老父と娘のぎりぎりの生活を見つめる。体を起こせないほどの強風で、見ているだけで体が疲れてくる。ゴーゴーと吹き荒れる暴風で画面を絶えずかきまぜ、ありとあらゆるものを空中に飛ばしながら長回しで撮影する。父子は毎日同じ服を着て働き、生きるために夕飯には一つのじゃがいもを分けて食べ、服を脱いで眠る。これは彼らの日常というより、作法に支配された儀式のようだ。何か語りたい物語があるのかもしれないが、それよりは、表現したい映像のためだけにデザインされた世界にすぎず、すべてはタル・ベーラの芸術のために、死にそうな馬も強風も親子の生活もカメラの前に据えられている、本当はこれが正解かも。陰鬱でストレスフルな父子の人生は、そうであるほど映像の美しさを助長する。ニヒリズムを極め、ニーチェ的といえばそうなのかもしれない。
言ってしまおう、この映画は楽しくない、娯楽性ゼロ。
ぶっちゃけ、最初の30分は忍耐だ。何もおこらないし、面白くもなんともない。その後だって別に明るい要素はなくて、ただ風に翻弄され、破滅ににじり寄っていく時間軸があるだけ。それでも、そうであっても、この作家の作品は見るべき価値がある。モノクローム映像の特性を最大限に使った、黒白グレー濃淡で描いたステキに荒涼とした丘を、狂った気体エネルギーが吹きすさぶシーンの映像はこの上なく美しく、立ち枯れの巨木も、芋を洗う娘も、眼を剥いた年寄馬も、老父がズボンを脱がされるシーンさえ、映画として動かしてしまわずに、フィルムを1枚1枚止めてほしい、ちゃんと見せてほしい、と思うほどに計算されつくされている。
映画を観ていて、ひとつの映像がいつまでも心に焼き付くことがあるだろう、その感覚が154分継続する強烈な濃度をもつ痺れるような映画なのだ。昔映画学校の先生が言っていた。
「摂理があって撮る時は、映画の神様が手を貸してくれる。突然絶妙な角度で光が差したり、凪だったのがいい波が立ったり… 奇跡としか思わないことがフィルムに映せたら、その映画は神様に愛されているってことだ。」
タル・ベーラの作品には必ずそういうシーンがある。後でメイキングなどで気になるシーンの事情を確かめると、関係者が身震いするほどに奇跡が起こっているらしい。ニーチェの神は死んでいても、タル・ベーラの映画の神は執拗なほどに彼を溺愛している。
別の神様の仕事、マスターはカスタマーに負けない
神田の万世橋に元駅舎を利用した施設がある。そこに三軒茶屋のコーヒーの名店 が入っている。最初にその店に行ったのは年末、100グラム5000円を超える大物が数種類、すごいねえ、高いねえといいながら、まあまあのストレートコーヒーを豆で注文し、別に自分たち用のテイクアウトを頼んだ。店はそこそこ混んでいて、テイクアウトを待っているお客もかなりいた。でも、でも、でも。コーヒーはそう簡単に供されない。 バリスタは白いシャツに黒いエプロン、めがねをかけた細見の青年で、穏やかな微笑みを浮かべてコーヒーを商う知的な感じの人だ。
注文を受けると、コーヒーを焙煎し、適度に挽いて、しゅんしゅん沸いたポットを傍らに手を止める。一人一人の注文は違う。ようやくコーヒーの粉をフィルターに入れ、ほんのわずかお湯を注ぐ。下の容器に漏れ出ないくらいの微量。目はコーヒー豆の膨張と、腕時計の秒針を見比べている。チッチッチッ…… カウンターのこちらまで聞こえてくるわけではないのだけれど、彼は膨張が収まる数十秒を時計で測って、一定の時間を空けて、機械仕掛けのように正確にほんのわずかずつお湯を落としていく。カップ一杯までの道のりは遠い。
すべては腕に巻きついたオメガのスピードマスターが決める
とでもいうように。お店がお客で一杯でもひるむことなく時間をかける。みんなスタバくらいのスピードでコーヒーが出てくるものと思っている。まさか一杯数十分もかけて抽出するとは思っていないし、21世紀のカスタマーはそんなに待てないのだ。でも、彼は負けない。6人の客全員が心の中で「早くしろ」とわめいているけれど、その無言の圧力にも負けず、主義を貫き通す精神力はすさまじい。スピードマスターを見つめながら、恐ろしいほどの時間をかけて、コーヒーを淹れる。仮に「まだですかあ、早くしてください」などという客がいたとしたら、きっとあの穏やかな笑顔で圧殺してしまうだろう。 永遠に近いほどの時間がたち、私のコーヒーが出来上がる。それは生まれて初めて経験する飲み物だった。
コーヒーはその昔、シャーマンが使う刺激物だったと聞いたことがある。普通に毒物にさらされて生きている現代人の私でさえ、そのコーヒーを飲んだとたんくらくらくらっと目が回った。濃厚な香り、苦味と酸味、甘味が同レベルで押してくる。美味しいと感じた後から感じたことのない感覚が起こる。味覚では処理しきれない複雑なコク。もちろん合法のコーヒーだ。時間をかけて、絶妙な温度でベストに淹れたコーヒーというものがどういうものであるか、待っている時間には想像もしなかった。スピードマスターの流儀には、どうしてもそうでなくてはいけない理由があったわけだ。特別の豆には特別の方法が必要。時間などかけてどうにかなるなら、かければいい。時間などいくらでも使えばいい、これがまた飲めるなら、いつまででも待とう。
でも、あれから一度も神の手をもつマスター氏に出くわさない。万世橋のカフェでオメガのスピードマスターをしたバリスタを見かけた方、ご連絡お待ちしています。