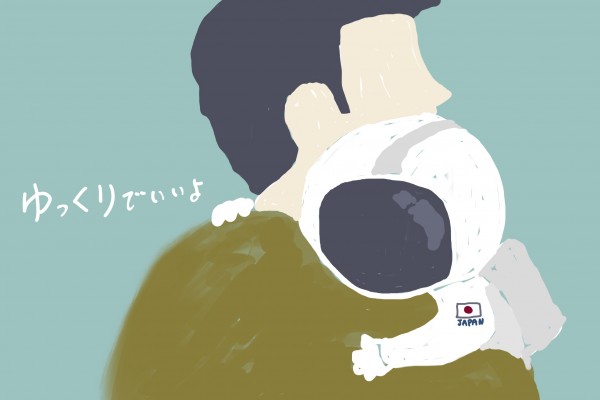表紙の顔を触れないほど
紙に臨場感を持つ人もいる
————–
あなたは雑誌の表紙の顔を触れますか? タレントやミュージシャンの大きな顔写真が表紙に使われていることがある。そのある音楽雑誌は、おじさんミュージシャンが表紙だった。それを手に持っている女性が「持ち歩きたくないんです」と言う。理由は、顔に触りたくないんだ。手にもって歩くと、おじさんの目を指で触ってしまうし、鼻や口に指が入ってしまうし、ヒゲには触りたくない。でもその雑誌の中身は読みたいから買ったけど、表紙をめくるときに触ってしまうから、それが嫌で嫌でしょうがない。
敏感な感性の人もいるのです。臨場感を感じすぎて、写真に触れられない感性。この人にとっては、雑誌や写真集は生き物も同然だ。ほとんど生身の人間のような感覚で触れている。あなたはどうですか? 気にする人と、気にしない人といるでしょうね。生身のような感覚で触れている人にとって、デジタルはどうなのかな。iPhoneやiPadでも顔の部分はタッチしたくないのかな。
写真に触れられない感性の人がいるというのは知っていました。だから昔から本の表紙に著者の写真をデカデカと出すデザインには反対してるんです。『芸術起業論』の村上隆さんなんて、強烈ですよ。全面が顔ですから、どうしたって触ってしまう。好きな顔だったらいいんでしょうけど、だいたい作家の人で好きな顔なんてそうはいないでしょうから、写真に触れられない感性の人は困ってしまいます。
雑誌だけでなく、本の場合もよくあります。著者の顔写真を表紙に出すのは、本屋で平積みされている時のアイキャッチのためです。人間は本能的に人の顔に反応するように出来ていますから、美人かどうかは関係なく、顔があると目がいきます。おっ、と目が止まって、知ってる人かどうかを確認してしまうのです。よく赤ちゃんの写真を使っている本もあります。あれもアイキャッチで、しかも嫌悪感がないから赤ちゃんなんですね。
女性の写真ならまだましなようです。その女性も、女性だったらまだ触れると言ってました。デカい顔を使う時は注意です。このように生身と紛う(まがう)くらい臨場感をもって、紙の写真を扱ってもらえるのなら、写真集の物質としてのインパクトはすごいものでしょうね。写真サイズが大きければなおさらです。これからますますデジタル全盛になっていきますが、こういう臨場感の力を考えると、物体として存在する紙の写真集はまだまだなくならないでしょう。
(約1004字)
Photo : Catherine