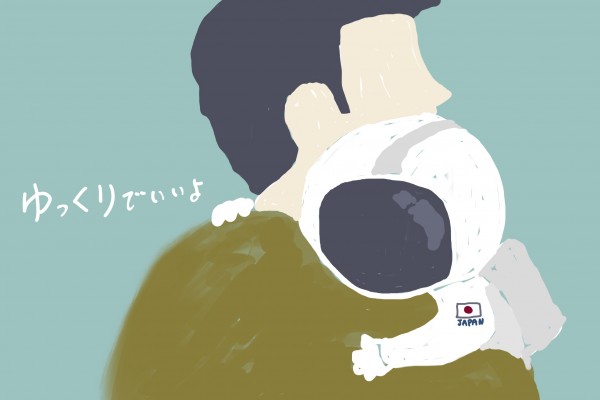【インド旅篇 その4】
頑固な医者嫌いが、医者に頼ることにした理由
死神と出会った、あの峠を越えてから4日が経つ。しかし体調は良くもならず、かといって悪くもならず、平行線をたどったままだ。相変わらずひどい下痢で、30分おきにトイレに駆けこまければならない。室内で安静にしている分には大丈夫だが、外では活動できない。焦りがつのる。旅の期間は20日間だが、そのうちの5日も寝たきりだと、さすがにいろいろ予定がこなせなくなってくる。せっかくインドに来て、「寝たきりで終わりました」では、何をしに行ったんだという話になってしまう。
医者にいかず、薬も飲まない主義。自然治癒派であるぼくも、さすがに信念がぐらついてきた。「医者で注射1本でも打てば、すぐに良くなるかもしれない」もちろん、このまま安静にしていても、何日かかるかわからないがいずれ完治するだろう。自分ひとり、誰にも迷惑をかけない状況ならそれでもいいかもしれない。けれど今は旅仲間がいる。ほかの3人のメンバーには気を使わせてしまうだろう。チームでやりたいこともできなくなってしまう。足をひっぱってしまっては、しのびない。今は、ぼくだけの体じゃないんだ。
このペースだと動けるまでにあと10日も15日もかかってしまいそうだった。仲間への配慮と、旅の成果とか効率とかそういうもののために、医者嫌いは病院にいくことにした。この選択が2度目の死の淵をさまよう事件となるのだが。
その病院というか診療所は、宿から歩いて行ける距離で、「日本語と英語ができる医者」という触れ込みのところだった。ぼくは英語がうまくないので、弱ってる時には特に日本語が通じると助かる。行くと、予想以上に小さな6畳くらいの診療所で、改装中だった。ドクターは自宅にいてそこで治療してくれるよ、と作業中の大工さんが面倒くさそうに教えてくれた。
昼13:00。ドクターの自宅(こちらは4階建で大きかった)で、診療が始まった。激しい高熱と下痢がもう5日間も止まらないんです。英語と日本語で症状を伝えた。しかし、日本語はまったく通じず、英語もあやしい。やっぱりか…。日本語と英語ができる医者という宣伝は、ウソ。よくある集客目的の誇大広告だった。 ドクターは、助手に指示し、ぼくをベッドに連れて行く。いきなり点滴が始まるようだ。注射1本と薬程度ですぐに帰れると思っていたのに、何やら大事になってるようだ。大病をしたことのないぼくにとって、人生で初めての点滴だ。いや、ちょっと、もうちょっと心の準備をさせてくれ。6時間もかかるなら、トイレにも行かせてくれ。そして、注射刺すなら消毒くらいしてくれ。
咳をしても一人
そうこうしているうちに、ドクターはふらっと外へ出かけて行ってしまった。たぶんご飯でも食べに行ったのだろう。助手は、ドクターがいなくなったとたん、のびのびと仕事をしだした。ノリノリで歌をくちずさみながら、点滴の準備をしてる。さー、いくよ!らしきかけ声で、ぼくの右手に点滴の針を刺した。痛いけど、男たるもの、このくらいたいしたことはない。よし、あとは6時間、このまま寝てればいいんだな。
パチンと家の電気が消えた。助手までも、出かけてくると言う。「ゆっくり寝てな。俺も、ちょっとご飯食べて、昼寝でもしてくるからさ」日中とはいえ、家の中は薄暗い。一人きりなのもあって、ちょっと怖いので、電気はつけといて欲しいなぁ。まあ、寝てしまえば、6時間なんてあっという間か。いや、でもこんなアウェイな場所で眠りこけてしまうのは危険だよな。
残された部屋で一人、そんなことを考えていると、体に異変を感じた。寒いのだ。夏なのに寒いというのも変な話だ。「あれ? さっきまで暑かったのに」外の気温が下がったのかな、と思い、足元にあった毛布をかけた。いや、毛布をかけても寒い。体がブルブル震えてきた。
この点滴のせいか! こういう治療法なんだろうか。ものすごく寒い。体温が急激に下がっているのを感じる。こんな激しい治療なのに、患者を一人きりで放置とは…。さすがインドはワイルドだな。郷に入りては郷に従え。なんとかおとなしく耐えよう。
15分は耐えた。寒すぎる。横になってじっとしていては体温低下がすすんでしまう。起き上がって、座りながら体を揺らし、自家発電さながら少しでも体温をつくろうとした。
だんだん目の前が黒っぽい緑になり、意識が遠のきだした。前回、死神に出会ったときの状況と同じ。まるで氷河の海に投げ出されてしまったタイタニックの乗客のようだ。あの映画の主人公が寒さで力つきる場面が頭から離れない。ガタガタ震え、体温が急降下しているのがわかる。くそ、あの助手、俺の体に何を打ったんだ…。この点滴の液体はなんの薬なんだ。ものすごい恐怖が襲ってくる。限界だ。助けを呼ぼう。
「エ、エクスキューズミー…」
くそ、声も出ない。エクスキューズミーとか、慣れない英語つかってるから声が出しにくいんだ。母国語でいこう。一番声が出るセリフはなんだ?
「おーい…」
ちくしょー、小さい!
「助けてくれ…」
声が出ない。
「ヤッホーー…」
お、これは少し声が出しやすい。
「ヤッホー、ヤッホー…」
声をふりしぼりながら、ガラスのパーテーションをバンバンと叩く。
だれか気づいてくれ! ふと目をやると、ボタンを発見。これだ、これで助かる。やっぱりあるのです、ナースコール。さすがにこんなリスキーな治療をするのに患者を放置しないよね。ガタガタ震える指先に意識を集中させ、ボタンを押した。パチン…。すると、目の前がパッと明るくなった。そう、これはなにかの比喩ではない。このボタンはただのライトだったのだ。
もうだめだ! 自分でなんとかしなければ。いつまで他人に頼ってんだ。情けない。自分のことは自分で守る。自分の頭で考えるんだ。こんなところで死んでたまるか。点滴を外すか。いや、外して血が飛び出てきてもまずい。出血多量で死んでしまうかもしれない。点滴をどう対処したらいいのか、わからない。自分の医療知識のなさを後悔した。
座して死を待つより
ドクターが帰って来ないなら、こっちから探しにいくしかない。点滴袋を手に持ち、動かない体を強引に動かしながらベッドからずり降りる。「うおぉーーーい、ドクタァーーーーーーー!」叫びながら、意識を失わないようにしながら外を目指す。
だれにも気づかれずに、座して死を待つよりも、あがいてみせる。俺はここにいる。膝がガクッと折れ、床に倒れる。点滴袋は、高い位置に保ったほうがいいんだよね、血が逆流しないように。とか考える冷静さも残ってる。よし、生き抜いてやる。一歩一歩、明るい外の世界へ進んで行け。
この家の重いドアを開け、ストリートに出る。ここで、もう視力がなくなった。真っ暗、音だけの世界。通りの騒音が聞こえる。このままフラフラと進み出ては危ない。バイクにひかれてしまう。背を壁に当てながら、ガクガクと揺れる体勢を保つ。まだ半分くらい液体の入った点滴袋を両手でつつみこみ、拝むような形で力の限り叫び続ける。
「Call me Doctor…Call me Doctor…医者を呼んでくれ!」
ストリートは、バイクのクラクションや雑踏。音の洪水。この病人のかすれ声など、かき消されてしまう。だれか俺を見てくれ、気づいてくれ! 俺はここにいるぞ。
ポケットをまさぐる10本の手
「ジャパニ、ジャパニ?」わさわさと声が近づいてくる。人間の体がボンボンとぶつかってくる感触。熱量で10人くらいに囲まれてるようだと感じる。全身を探られてる。ぼくのズボンのポケットに手を入れられている。金目のものを持ってないか、探ってるんだ。ちくしょー、弱者には容赦ないな。「1ルピー、1ルピー」物乞いの子どもも混じっているようだ。腰にまとわりつく。もう、なんでも持っていけ。「Call me Doctor…Call me Doctor…」ガタガタ震えながら念仏のように、唱え続ける。
ちなみに細かいことを言うと「Call me Docter」だと「わたしを医者と呼んでくれ」になる。「わたしを医者と呼んでくれ。頼む。わたしを医者と呼んでくれよ」と必死に訴えていたわけだ。そういえば、「ドクター!」とぼくに向かって言ってくれた男がいたような気が。
進むか、とどまるか
ここバラナシは交通事故でひかれた死体があっても、一瞥してみんな素通りしていく場所だ。人の死などたいして重くない。それぞれが自分が生きるので精一杯なんだ。生きるためには、他人のお金も盗る。頭と体の弱い奴がいたら、騙す。そんな輩が多くいる。そんなストリートで無防備な弱った体をさらすことは、ハイエナの群れに肉を差し出すようなものだと言う人もいる。それはわかってる。でも、多くの人の目にさらされる場にでれば、だれか一人でも救いの手を差し伸べてくれるかもしれない。奇跡が起きるかもしれない。だれにも気づかれず、ベッドの上で体温低下で静かに死にたくはない。ぼくは表現者だ。叫べ。力の限り叫ぶんだ。
人の輪が大きくなる。20-30人は集まっていそうな気配だ。だれか、心の優しい人がいてほしい。弱いものから泥棒する奴だけの街じゃないだろう、この聖地バラナシは。たのむ、だれか医者を呼んできてくれ。
1時間も叫び続けた頃だろうか。「What’s happen! どうしたんだ!」大声を上げて、助手が走って戻ってきた。ぼくを抱きかかえ、ベッドへ運ぶ。「すごく寒い…。急変したんだ…」消え入りそうな声で訴えるぼくに「なんだって! じゃあ、この注射だ」。新しい注射を点滴の管に流し込んだ。体の中の血管が痛くなる。注射の刺し口が痛いのはあるけど、痛いものが流れ込んできる感覚は初めてで、不安は募る。「これは何の薬だ…?」聞いてるのに、ヒンズー語で何を言ってるかわからない。
しばらくすると、体温が戻ってきた。体の硬直もやわらいできた。意識もはっきりしてきた。「どうだ、これで治っただろう」得意げな顔で助手はひとり、チャイという紅茶を飲む。ぼくにはチャイをくれなかった。
ケツを出せ、あれしかない
ほっと一息したのもつかの間。今度は、体が燃えるように熱くなってきた。熱い、熱いと訴えるぼくに、助手は余裕の笑顔。「うんうん、体が熱くなっていいんだよ。No,problem. 問題ないよー」いちいちきみは大げさなんだよ、と笑っていた。それがついにぼくがヒューヒュー言い出して、だまってしまったら、心配になったのか、ぼくの額に手を当てて、驚嘆。「やばい! Too Hot! Very hard fever. この熱やばいよ!」体温が上がり過ぎて危険な水域らしい。もう、だから言ってるでしょう!
「ああ、もう、こうなったら、あの最終兵器を使うしかない」
頭を抱えて助手は叫んだ。彼にはもうご機嫌な歌を口ずさむ余裕も、チャイを飲む余裕もない。頭から汗がしたたっている。
「ヒップを出せ! この注射で熱を下げる!」
太い注射をだしてきて、うつぶせに倒れているぼくのズボンをずり下げ、左のお尻にグサッと刺した。 「うあーーーー! 痛ってーーーーーッ」 ショックでぐったりしていると、おいおい、表の人だかりはなんだ、とドクターが帰ってきた。
「お前、何の点滴したんだ? もしかしてこれ打ったのか?」
「いや…まあ…ノープロブレムですよ」
それらしきことをドクターと助手で言い合っている。疑うのも良くないが、おいおい、やっぱり医療ミスなんじゃないの…。しばらくして、さっきの最終兵器の注射がきいたのか、熱が下がってきてだいぶ楽になった。そして最後にもうひとつ、違う種類の点滴をするという。もうこれ以上、彼らのおもちゃにされちゃたまらない。ノー、と力強く断った。
6時間戦争の終わり
とっくに日は暮れた夜20:00、仲間3人が病室に迎えにきてくれた。
「だ、大丈夫ですか!」
仲間たちは、お尻をだしてぐったりしているぼくをみて、ただならぬ空気を感じたようだ。明らかに、治療前よりも弱っている。だが、とにかく仲間が来てくれれば安心だ。この6時間のあいだに起きたことを思い返して、ぼくは笑いがこみ上げてきた。笑いながら、涙も出てきた。もし、あのとき助けを求めて外へ出なかったら、今頃どうなっていただろう。
6時間、何も飲んでないし、叫び続けたもんだから、脱水症状ぎみだ。
「ぼくの水、飲みますか?」
察した仲間の河西くんがペットボトルをすすめてくれたが、ちょっと考えて「もう少しで帰れるから、いいよ」と断った。病人のぼくが彼に変なものをうつしてしまったらいけないと、思いとどまったのだ。助手は、ぼくが危機を脱した様子に安心したのかニコニコ顔。「いつまでお尻出しているの。お行儀悪いよ」なんて茶化してくる。
教えてくれ、病名は何なんだ?
「それについては、あとでドクターから、お話があるよ」
助手は、やっと終わったねと手をさしのべ、ぼくを起こした。
「ドクター、病名を教えてくれ。ぼくは何の病気だったんだ」
まだおぼつかない足取りで、ドクターにつめよった。
「Listen. いいか、心して聞きなさい…」
ドクターは神妙な面持ちだ。
「Yes. Please… 本当のことを教えてくれ」
あれほど死にかかるほどの治療を受けたのだ。重い感染症なのかもしれない。こちらにも緊張が走る。
「Your sick name is… テンテキ… ハライタ… ゲリ」
「は…? て、点滴…。病名が、点滴?」
「と、とにかく、You are STRONG MAN. No, Problem!」
あの治療に耐えたとは、お前は強い男だって言ってるのか? わけがわからない。
「あのさ、そんなことより、今日は一泊入院していきなさい」
「ノー、断る」
「なぜだ、どうせ国に戻れば保険で治療費が出るんだろ、いいじゃないか」
「そういう問題じゃない」
死にたくないんだ。
「わかった。じゃあ、明日は朝11時にまた来院しなさい」
「ノー、それも断る」
「なぜだ、医者が言ってるんだぞ。また悪くなったら、どうするんだね」
「そのときになったら、また考えます。ぼくはSTRONG MANなんでしょう?」
自分のことは自分で守る。これはぼくの人生なんだ。ぼくは、仲間に肩を借りて、宿に歩いて帰った。
帰り道で、今日の長かった一日を回想していた。何の意味があって、今回の危機が起きたのだろう。もしかして天は、ぼくを表現者として再生させるために、この不可解な事件を起こしたのかもしれない。
あのとき、だれもいない異国の薄暗い一室で、間違いなく人生の岐路に立たされた。じっとだれかの救いの手を待つのか。それとも、ストリートに出て行くのか。選択を迫られ、ぼくは後者を選んだ。どんなにダサくたって、リスクがあったって、そのときの精一杯で声を上げること。己の足で前に進むこと。そうしたら思いが通じるかもしれないこと。奇跡が起こるかもしれないこと。この度はドクターマシラと助手に感謝したい。おかげで表現者としての原点に立ち返ることができました。
Photo by N.KUMAGAI / J.FUKAI / M.KAWANISHI