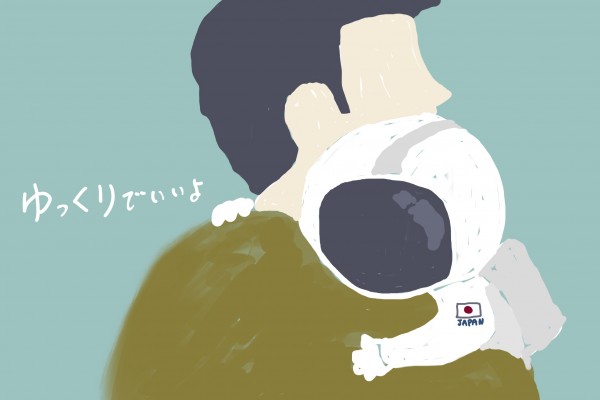はいはい、聞こえてるよー
昔のアルバムどうしてますか?
このところまた、部屋のモノを断捨離しています。だいぶ減ったのですが、収納の大きな位置を占めているのが、幼少のころの写真アルバム。今まで手をつけられずにいたのですが、意を決してメスを入れました。
昔ながらのアルバム。無駄に大きく分厚く重いんですよね。デジタル化して、あとは念のため厳選した写真のみを紙で裸で持っていたほうが省スペースになります。 デジタル化する作業をチマチマやりながら、思いだすことがたくさんありますね。こんな小さな頃の写真が出てきたり。チビ次郎。目と耳が大きくて、宇宙人っぽい顔してます。

岩手県盛岡市。家の庭にて
ぼくの職業観をつくった吹奏楽部の話
まあ、それはいいとして、アルバムをめくる手が止まったのは、小学生のころ、吹奏楽部をやっていた時の写真です。

小4のころ。最後の大会。最後列一番左が深井
子どもの頃、働く大人とリアルに接する機会と言えば、駄菓子屋さんか小学校の先生くらいしかありませんでした。大人になったら、働かなきゃならないんだよなーとはなんとなく考えたこともあるけど、働くのがどんなことなのか、小学生のころは、まったくわかりません。
それでも先生に恵まれたおかげで、大人になるってまんざら悪くもなさそうだと思えた。ところどころで、すばらしい先生ばかりに出会ってきたなあ、と。
365日、音楽漬け
熱血先生あらわる
その1人が新村(しんむら)先生。ぼくは吹奏楽の課外クラブに入っていました。埼玉県の田舎の県立小学校です。友達がやっていた少年野球やサッカーもそろばん教室も面白そうに思えず…、本当はバスケをしたかったけどその地域にはミニバスがありません。しかたなく、兄の真似をして吹奏楽クラブに小3のころ、入りました。
本当は、兄と同じドラム、打楽器がやりたかったけど、「俺の真似をするな。それにドラムは人数いらないから間に合っている」と言われ、トランペットになりました。
新村先生は、30歳手前の若手。スーツにネクタイ、髪は七三分けで眼鏡、ひょろっとした体型という、「ザ・サラリーマン」という見た目でしたが、中身はとても熱い男でした。
先生は、普通に担任クラスをもっているのに、放課後は夜遅くまで練習。真っ暗になった学校を最後に出るのは、いつもぼくたち吹奏楽部でした。毎日、夜道を迎えにきてた親たちは「先生、いつも遅くまでありがとうございます」と感謝していました。夜の学校は怖くて、みんなでお化けだなんだとキャーキャーいいながら楽しかった。
土日も夏休みも練習。先生は、休日がほとんどなかったんじゃないかな。それだけ働いても公務員の給料は変わりません。課外クラブはボランティアですから。大会など遠征に行く時も自腹です。 新村先生は、本当に音楽が好きで、教えるのが好きで、そんな吹奏楽漬けの生活を、新人のころから5年も6年も続けていたのです。
生徒を夜遅く帰らせることに対して、上司から注意されたこともあったようです。同僚からも「スタンドプレーはやめてもらえるかな。ぼくらがサボっているみたいじゃないか」と足をひっぱられたこともあるようです。 大会遠征のときには事故のリスクもあるし、公務員の先生がリスクを背負ってあれだけやっていたのは、そうとう熱のある人だったのだなと。
真夏の練習はハードでした。大ホールと同じようにするため、音が反響しないように、音楽室の床や壁全部を毛布でおおって練習することもあります。これを真夏に(あの時代は公立小学校に冷房がなかった!)音楽室を締め切って何時間もやるのですから、汗だくで意識がもうろうとしてきます。肺活量が大事なので走り込みをしたり。生徒も大変ですが、先生だって大変です。
それだけ練習しても、県大会のレベルは高く、毎年2位の銀賞で終わっていて、新村先生は関東大会へ出場したことがありませんでした。
新村先生、勝負の年にまさかの異動
「来年こそは、この代なら勝てるのではないか」というところで、新村先生は、隣町の小学校に異動になってしまいます。
もちろん、クラブ存続が危ぶまれました。部員は40人いますが、顧問と指揮者がいないのです。指揮者は生徒ではダメですし、顧問の先生がつかないと正式なクラブとして大会出場ができません。
新しくやって来た音楽の先生は、上田先生(こちらは仮名にしときます)といって、顧問を頼むと
「あたし、いやですよ」
あっさり断られました。少し化粧の濃い、前髪をカールさせた20代の若い女の先生でした。
「あたし早く帰りたいし、余計な仕事を増やしたくないです。土日も仕事なんてありえないし、なにか事故でもあったらリスクです。そんなの、なんのために公務員になったか、わからないじゃないですか?」
当時は、「なにそれ」と反発しました。「生徒の希望を叶えるのが先生の仕事でしょう、ふおかしなこという人だな」と大人の事情がわからなかったんですね。いまなら先生の気持ちもわかりますけども。そりゃ、仕事増やしたくないですよね。いくら前任の先生が積み上げてきた土台があるとはいえ、荷が重いです。本当に好きじゃなきゃ、顧問はできません。
新村先生がいるうちに金賞を獲らせてあげることはできなかったけど、ぼくらは、どうしても先輩たちが卒業するまでにぜったい金賞を獲りかたった。40人の生徒とその親で上田先生に何度も懇願し断られをくりかえし、クラブ存続だけはなんとかしてもらいました。
「わかりました。しかたありません。1年間だけですよ。言っておきますが、あたしは名前を貸すだけです。あとはなにもしませんからね!」
「はい、コンクール当日のみ、指揮をしてくれるだけでいいです。その1日だけでかまいません。練習は自分たちでできますから」
そういう約束で、最後の年がはじまりました。上級生が、今まで続けてきたやりかたで練習。休日は先生がいないので学校をつかえません。公民館、コミュニティーセンターを借ります。ときどき、新村先生も来てくれてアドバイスをしてくれました。
「どうせ小学生だけでは練習が続くわけない。子どもはすぐに飽きるし、集団はすぐに崩壊するだろう」
上田先生は、たかをくくっていました。けれどそれが、半年を過ぎても生徒40人が欠けることなく放課後遅くまで練習を続けている。その姿をみて、なにかを感じたようで、たまに(月に一度くらいですが)顔をだしてくれるようになりました。
「あ、あたしも指揮の練習が必要だから… 」
少し照れながら、大会近くなると、ほとんど毎日、来てくれるようになり、上田先生なりの意見もくれるようになりました。
そして、大会当日。吹奏楽部、最後のコンクール。上田先生は、いつも以上に気合いの入った化粧と、前髪をカールしていました。新村先生も他校の顧問として会場に来ていました。
ぼくらは舞台で全力を出し切った。ちょっと音がずれたところもあったので「うーん、今回もダメかもね、でもがんばったよね… 」という空気。しかし、予想に反して結果はなんと、金賞に選ばれたのでした。
先輩の女子たちはみんな泣き崩れ、ぼくはヘラヘラ笑っていました。悲願の金賞。関東大会出場です。新村先生が積み上げてきた基礎が、去った後に花咲いたのです。
「金賞おめでとう、よくがんばった! ぼくが指揮してた頃よりずっといいですよ。みんな上田先生の指導のおかげだね、感謝しないと」
新村先生は、上田先生を立てていました。
勢いづいて、このまま目指すは全国優勝か! というところで関東大会では3位の銅賞。そこで吹奏楽部は解散になりました。
思い切り吹きなさい
自分の音色をみつけなさい
こうして先生をみるだけでも、「働くっていろんなスタンスがあるんだな」と考えさせられます。新村先生のように、好きなことに脇目もふらず、自分のために子どもたちのために、外野の圧力も吹き飛ばして全力でやる大人。それが先生として当たり前と思っていたけど、違うタイプの先生もいるのだなと。子ども時代は、上田先生のスタンスは理解できませんでした(もちろん、今はわかります)。好きでもない仕事を、なんでやってるんだろう。これだけ頼まれて子どもたちに協力しないなんて。数ある職業の中で、この人なんでわざわざ教師を選んだんだろう、と不思議でした。
あと思ったのは、大会で勝ったのは確かにうれしかったけど、思い出すのは、その過程での泣き笑いの日々でした。そういう1つの目的に向かって、正解がないものを、みんなであーだこーだ言いながらなにかやるのがぼくは好きなのかもしれないなと。
と同時に、新村先生から言われたこと。
「上手い下手はさておき、まずは思いっきり吹きなさい。そして自分の音色を見つけなさい」
これがずっとひっかかっていました。 吹奏楽では、トランペット担当は何人もいます。ぼくは実は難しいパートは吹かずに顔芸だけ。口パクというやつです。あとはうまい先輩に任せて… という場面はよくありました。
「外して、みんなに迷惑かけてはいけない」
ぼくは最年少なのもあって下手だったから、音を外すくらいなら、吹かないほうが全体への害は少ないです。そしてひとりくらい吹かなくても、観客からは全然わからない。勝負しないで安全な選択をしてたんです。
「キミ、優勝校の子でしょ、すごかったね。うまかった!」
会場の廊下とかで他校の子から話しかけられたりもしたけど、すごかったのは先輩たちや他のメンバーで、ぼくはみんなにおんぶにだっこで、連れて行ってもらっただけ。 吹いてない箇所もあるし、吹いてもソロではないので、自分の音色がわかりません。集団のなかだと埋もれてしまう。自分が吹いていないのに吹いてると錯覚し「なんか、おれ、うまくなったかも!」なんて勘違いしてしまうこともありました。
国語の時間に教科書をひとりずつ音読するのでさえ、緊張して声が裏返ってしまう子だったけれど、60人のなかのひとりとして舞台に立つ時は、1ミリも緊張しないものなんです。陰に隠れるって楽。でも、その立場に自分の未来はないと直感しました。
(自分の音色を見つけたい)
当時はその気持ちを言語化できなかったけど、そんなようなことをモヤモヤ考えていました。
たぶん、最初にこれも直感でトランペットなどの金管楽器よりも打楽器に惹かれたのは、責任が明確だったからかもしれません。たとえばシンバルは、ひとりしかいないので責任重大です。ジャーン!と鳴らすタイミングを外すと曲をすべてぶちこわします。
チームプレーでありながら、その中にソロがある、責任がある。そんな役割を、ぼくはやりたいのかもと気づきました。 そしてその後、中学になるとバスケに傾倒していくわけですが、バスケはシュートを打つとき、1対1をしかけるとき、ソロパートがあるんですよね。しかもプレイヤーが5人しかいないので、ひとりひとりの責任が重いです。音楽なら、オーケストラより5人バンド。このくらいのサイズ感はやりがいを感じます。
オーケストラの中の1人では、自分の音色が見つけにくいものです。大きな組織に埋もれてはいけないな。1人でやるとか小さなチームでやるとかして、自分の音をみつけたい。そう気づく最初のきっかけが吹奏楽部でした。
そういえば、新村先生はいま小学校の校長をされているそうです。ああいう熱すぎて、ある意味で公務員らしくない先生が、ちゃんと評価され出世できるなんて、日本の公教育も捨てたもんじゃない。すこしは希望が持てるんじゃないかな、と思いをはせる、今日はそんな日でした。
(了)
(約3999字)
PHOTO: Hans Splinter